「いや、お前はすごいよ」
「え、そう?」
彼はいつだって真剣な眼差しだ。
いつもぼくを肯定してくれる。
ぼくは彼と過ごす時間を、褒め褒め会と呼んでいて、毎月楽しみにしていた。
負け犬の傷の舐め合いだって?
うるせえ、ばか。
ぼくらはやらない理由を探してるんじゃなくて、明日も前向いてがんばるために褒めあってるんだ、だから負け犬だなんて言わせない。
つーかそんなこと言ってるやつには耳を貸さない。
「おれはでもマコト好きだなぁ。いつも誰よりもがんばってるじゃん、誰かのことを考えて、向き合って、逃げないでどうにかしようとする。だからすてきだよ」
「ありがと。そう言ってくれるのはお前くらいだからふつうに嬉しいわ」
「たぶんみんな思ってるけど、恥ずかしいから言えないだけだよ。でもほんと、マコトの素直に褒め言葉を受け止めてくれるところとかも好きだよ」
「いや、それを言うなら、お前のそのまっすぐな言葉にいつも救われてるし、めちゃめちゃいいなって思うけどね。こんな会話誰か知ってる人にきかれたらめちゃめちゃ恥ずかしいけど、でも、やっぱり心地いいし、すごく大事な時間だよ」
「こそばゆい! 全人類がこれくらい素直になって、ライバルだったり、友達だったり、後輩や先輩だったりに、きちんと素敵な言葉を届けられたらいいのにね」
「こそばゆいすぎる世界だなそれ」
彼はそう言って笑った。
あ、また一つ。
好きなところをみつける。
まことの、ちょっと感情を隠したそうなくしゃくしゃ笑顔。
彼はクールぶる。
全然クールじゃないのに。
いつも熱くて、周りが見えなくなってしまいがちなのに、なぜだかクールぶる。
お、いいなって思うところが、誰しもに対してある。
ちょっとしたお辞儀の仕方や挨拶の仕方かもしれないし、歩き方や口癖かもしれない。
きゅん、とする場面って、ささやかかもしれないけれど必ずあって。
でも僕らはその”きゅん”を当人には伝えられず、持て余してしまうことばかりだ。
だからぼくは、マコトが好きだった。
彼はときめきを逃さない。
言葉一つ丁寧に、好きを伝えてくれる。
ぼくはそれに、憧れる。
誰かに感じたときめきを、いいなって思うポイントを、もっときちんと、すぐに、まっすぐ、いやらしくなく、素直に伝えられたらどれだけいいか。
髪型一つ。
拳の握り方だっていい。
喋るときの抑揚の付け方にさえ、ときめくポイントはあって、そのささやかな”きゅん”を大事にして、ただそれを丁寧に伝えることができたら、どれだけ幸せで、豊かだろうか。
憧れる。
そんな彼が、まぶしくてたまらない。
だからぼくは、彼が好きだった。
彼と一緒にいると、ぼくはもっと素直になれる。
好きを伝えていいんだって、それがどんな小さいものだって言ってしまっていいのだと思える。
「ありがとね、まこと」
「突然どうしたの、うれしすぎるんだけど」
「いや、ごめん。本当に真剣に言わせて。まこと。いつも一緒にいるぼくに興味を持ってくれてありがとう。携帯をいじらずにいてくれてありがとう。出会い頭に服を褒めてくれてありがとう。ぼくの選択をいつも否定せずにいてくれてありがとう。目を見て話してくれてありがとう。こんなんじゃ足りないけど、こんなことを言ってもいいんだって思わせてくれるくらい、いつもぼくのことを褒めてくれてありがとう。素直に受け取ってくれてありがとう。これからもずっと、良い友達でいてくれたら嬉しいです」
「ん。ありがとう」
まことは優しく微笑む。
一瞬迷うように口を閉じて、再びぼくの目を見て。ゆっくりと話し出す。
「わはは、ごめん無理泣く」
そう言うと、まことは笑いながらポロポロと大粒の涙を流した。
バカみたいって?
ぼくらはいつだって、大切にされたい。
きっと大切にするの定義が重すぎるぼくやまことみたいな人間にとって、生きることはあまりにもしんどすぎる。
だから、大切な誰かが見つかったのなら、泣いたってもいいじゃない?
だめかな。
ダメだな、これ以上話してると、余韻が台無しだ。
おやすみなさい。
きっと君にも、大切にしたいと思える大切な友人が見つかりますように。
いらないって?
そうか、それもいいかもしれない。
ぼくだって見つかるとは思ってなかったからね。






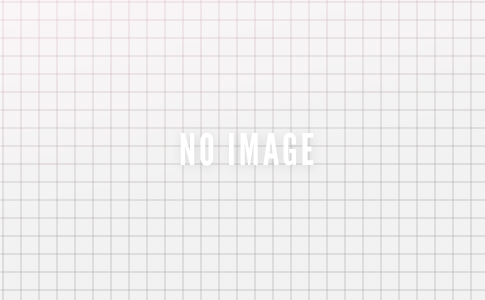









コメントを残す