「プレゼント、見つかった?」
「わぁっ、ゆきこ先輩近いっす!」
のけぞるぼくを見て、彼女はケラケラと笑う。
細い手首にはシュシュ、ネイルは水色とピンク。
ゆきこ先輩は今日もギャルい。
そしてめっちゃいい匂いがする。
シャンプーなのか香水なのかわからないけれど、とにかくめっちゃいい匂いがするのだ。のだのだ。
「たろう、あんた女の子に何買えばいいのかなんて分からないでしょ」
「そうですよ、だからゆきこ先輩に付き合ってもらってるんじゃないですか」
そしてあわよくばゆきこ先輩の好みも聞き出しとこうと思ってるんじゃないですか。吉田先輩のために。
これは男と男、……いや漢と漢の約束だから、ゆきこ先輩には絶対にナイショだ。
じぃ、っと、何か不服そうな顔で彼女がこちらをみる。
「あんた、心の声……、やっぱいいや」
「?」
「きょとんって顔すんなムカつく」
「えぇ、ゆきこ先輩怖い……」
「わたし、バカは嫌い」
「ほっ」
「は?? なんで安堵の表情浮かべたの??」
「アンド? ちょっとあんまり難しい言葉使わないでもらっていいですか?」
「何そのわたしが悪いみたいな顔。たろうちゃーん、一回歯ァ食いしばろうか?」
「ちょ、やめ、今日はあきちゃんへの誕プレ買いにきただけなんですけど!」
ぼくはお店の迷惑にならないよう、小走りで先輩から離れる。
「たろう」
しん、と音が聞こえてきそうな、冷たそうな声に一瞬ビビりながら、ぼくは恐る恐る後ろを振り返った。
「これとかは?」
「え」
「ほら、これ」
彼女が指さしたところには、ネックレスがあった。
薄いピンクに、花柄の。
「え、これですか」
「うん」
「彼氏でもないのにアクセサリーあげるのは重くないですかね……」
「あれ、まだ付き合ってなかったの」
ほんとに意外そうにゆきこ先輩がぼくをみる。
「なんかもっと、無難なものないですかね」
「好きな子の誕プレに無難なものあげるの?」
平坦だった。
押し付けるわけでも、責めるわけでもなく、ただひたすらに平坦に、彼女はそうきいた。
まっすぐとぼくの目をみて。
「あれ、もしかしてプレゼントあげるのも重いんですかね」
頭が少しずつ、右上の方から白くぼんやりしてくる。
そんなかんかく。
「わたしは何も言ってないよ、たろー。あんたの決めることなんだから、……あなたが決めないと」
どうしよう。
意気揚々と。ようようと。
大好きなあきちゃんに、何かしてあげたくて。
当たり前みたいに贈り物をするつもりだったけれど、あきちゃんのことを考えてはいなかった。
もしかしたらぼくのことを一ミリ好きになってくれるんじゃないかとか。
自分があげたモノで喜ぶあきちゃんをみたら、ぼくが嬉しいだろうとか。
そんなことばかりを考えて。
「たろーちゃん」
「?」
「心の声、今日も漏れてるよ」
「???」
頭上には、ハテナマークばかりが浮かぶ。
呆れた顔してこっちをみるゆきこ先輩。
右耳につけたイヤーカフが、光に反射して。
ゆきこ先輩は今日もギャルい。
「迷って、立ち止まって、落ちるとこまで落ちちゃえば? 大事なのはモノよりも気持ちだから。月並みだけどさ。ちゃんと選んであげな、たろーが」
ぼくは深くため息を吐きたくなった。
吐いてないけど。
「じゃあなんでゆきこ先輩はついてきてくれたんですか。プレゼント選び、手伝わずに突っぱねればよかったじゃないですか」
彼女に対しては、どうしても素直になれない。
なぜだかわからないけれど、悔しくて。
ちょっとだけ、すごく悔しい。
本当は感謝してるのに。
いつまでも付き合ってくれる、このギャルくて優しい先輩がぼくは大好きだ。
「ばーか。あまりにもひどいプレゼントだったらアキが可哀想だから。だから、だよ。っばーか」
「あれ、ゆきこ先輩顔真っ赤になっててリンゴみたいで可愛いですね」
「たろう、だから心の声漏れてるって……」
一瞬迷って、ぼくは立ち止まる。言うべきか、言わざるべきか。
いや、やっぱり言った方がいいな。
意を決して、口を開いた。
「いえ、これは心の声ではないんですが」
「よし、ぶっ飛ばそう」
「ちょ、ま、え?」
こうしてぼくの視界はブラックアウトしたのだった……。
迷って、立ち止まって、落ちてみる。
あきちゃんへのプレゼントはまだ、決まりそうにない。










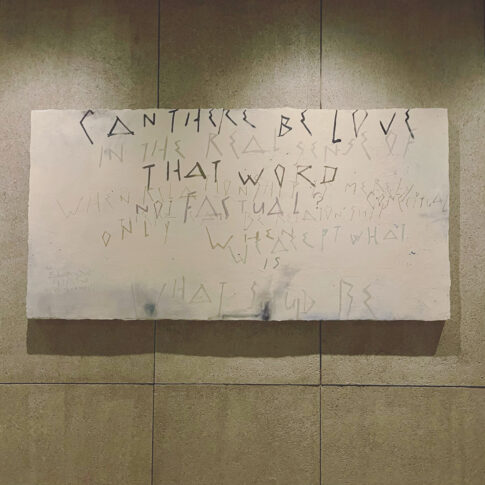




コメントを残す